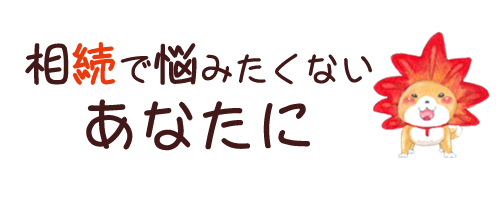認知症の発症後に家族信託を契約できるかどうかは、資産管理を考える上で重要なテーマの一つです。高齢の親を持つ世代にとって、突然の発症によって親の資産が凍結されてしまうリスクは、けっして他人事ではありません。本コラムでは、認知症になった後に家族信託の契約を結べるのか否か、ポイントを解説します。
結論から言えば、「契約できるかどうかはケースバイケース」です。契約には、契約者(委託者)に「契約内容を理解する能力=判断能力」が求められます。たとえ認知症と診断されていたとしても、すぐに無効になるわけではなく、本人の状態によっては可能なケースもあります。
たとえば、症状が軽度で、日常生活に支障がほとんどない場合です。医師の診断書などで「契約内容を理解できる状態である」と証明できれば、契約を結ぶことは可能です。実際、診察時の医師の所見や、本人の意思表示がはっきりしている様子を記録した書類が用意されることもあります。
逆に、進行した認知症で本人の意思確認が困難な場合は、家族信託の契約は難しくなります。このような状況では、家庭裁判所の手続きを経て成年後見制度を利用する必要が出てくることもあります。ただし、成年後見制度は財産の使い道に制限が多く、柔軟な資産運用がしづらくなるという課題があります。
そのため、家族信託は「早めの準備」が鍵となります。将来のリスクを見据えて、まだ判断能力がしっかりしている段階で契約を交わすことが、本人と家族双方にとって安心できる資産管理の方法となるのです。
たとえば、親が元気なうちに「子どもに自宅を管理してほしい」「将来の介護費用のために預貯金を使ってもらいたい」といった希望を持っているなら、それを信託契約で形にすることができます。認知症が進んでしまってからでは、こうした意向を反映させることは難しくなります。
本コラムでは、認知症になった後に、家族信託の契約を結べるかどうか解説しました。結論としては、本人の判断能力に左右されます。柔軟な資産管理を希望するなら、認知症の兆しが現れる前から家族信託を検討しておくことが安心につながるでしょう。