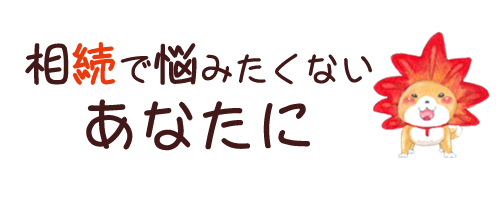葬儀信託とは、自分の死後に備えて、あらかじめ葬儀費用を信託という形で準備しておく仕組みです。高齢化が進むなか、身寄りが少ない方や家族に迷惑をかけたくないという思いから、関心を寄せる人が増えています。ここでは葬儀信託の基本的な仕組みについて、わかりやすく解説します。
葬儀信託は、主に銀行や信託会社といった金融機関が提供している商品で、契約者が生前に一定額の資金を預けておくことで、亡くなった際にその資金が指定された葬儀会社に支払われるという仕組みです。契約時には、葬儀の内容や費用の目安を決め、それに応じた金額を信託口座に預け入れます。
契約の流れとしては、まず金融機関と信託契約を結び、希望する葬儀社や葬儀の形式、費用などを事前に打ち合わせます。次に、必要な金額を専用の信託口座に入金し、契約完了となります。そして、契約者が亡くなると、遺族や指定連絡先からの届け出により、葬儀会社に直接費用が支払われ、葬儀が行われます。
このように、葬儀信託の仕組みはシンプルですが、いくつか押さえておきたいポイントもあります。たとえば、信託したお金は原則として葬儀にしか使えません。そのため、急な医療費や介護費用など、他の支出には利用できない点に注意が必要です。また、契約を途中で解約する場合、信託手数料が差し引かれる、あるいは返金されないケースもあるため、契約内容をよく確認することが大切です。
さらに、信託先となる金融機関や提携する葬儀会社の信頼性も重要です。万が一、葬儀会社が倒産した場合などに備えて、信託契約がどのように保全されているかを確認しておくことも、リスク回避のポイントになります。
近年は、家族や親戚が少ない単身高齢者だけでなく、「自分の葬儀は自分で決めておきたい」と考える人にも選ばれています。仕組みを正しく理解し、信頼できるサービスを選べば、安心して最期の準備を整えることができます。
本コラムでは、葬儀信託の仕組みや利用の流れについて紹介しました。契約内容をしっかり確認し、信頼できる金融機関・葬儀会社を選ぶことが、安心して活用するための大切なポイントです。